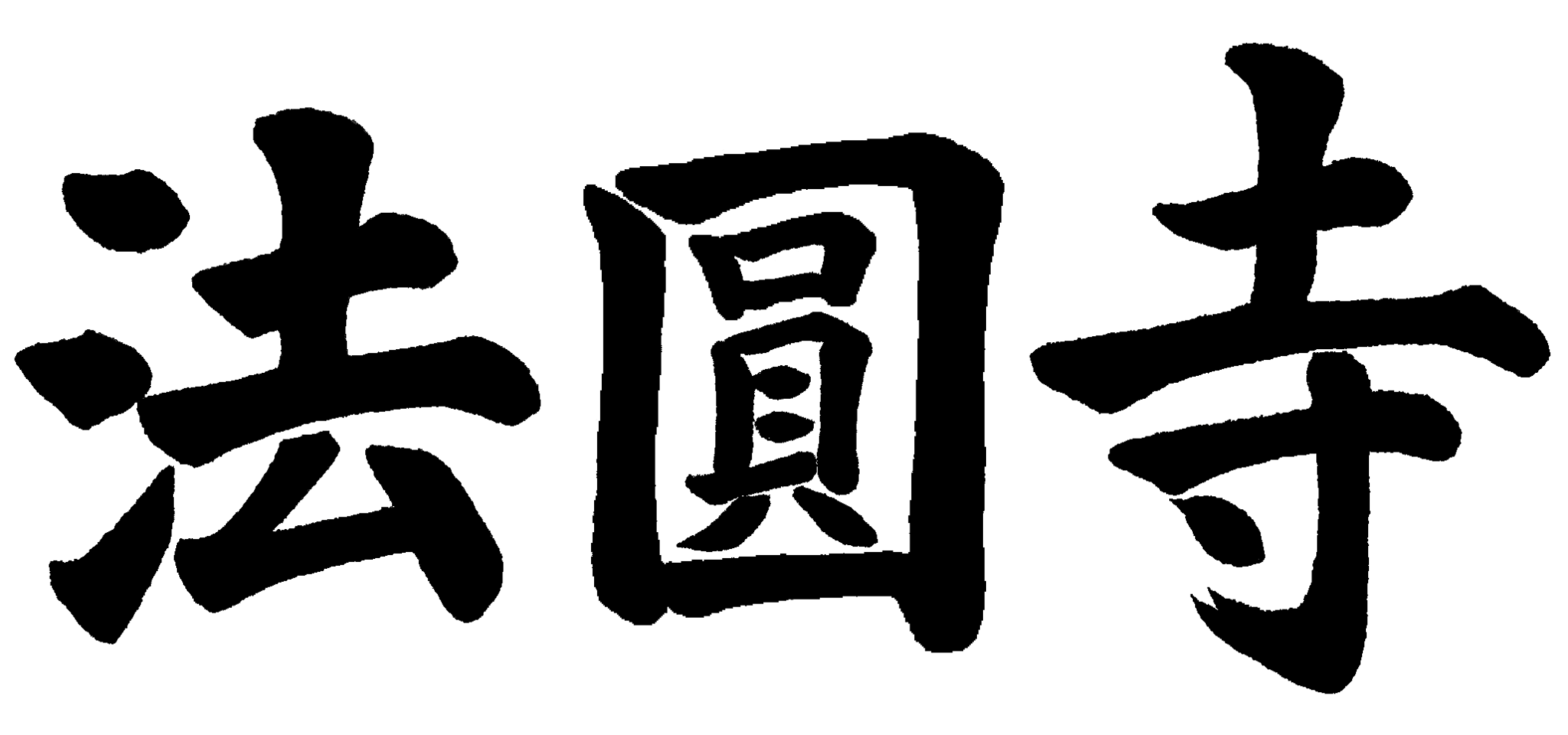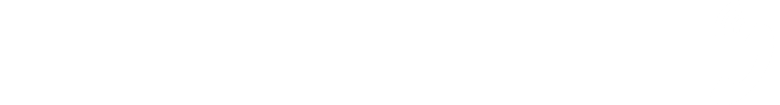第360回
善導大師
親鸞聖人は、インド、中国を経て、日本の自分にまでお念仏の教えを伝えてくださった七人の高僧を七高僧とお呼びになられ、尊んでおられます。その七高僧の第五祖に中国の善導大師がおられます。「お正信偈」にも
善導独明仏正意
善導独り仏の正意を明かせり。つまり善導大師だけが仏の本当の願いを明らかにされたと、親鸞聖人は善導大師をほめ讃えておられます。善導大師は『観無量寿経』の注釈書である『観経疏(かんぎょうしょ)』をお書きになって、それまでの『観無量寿経』というお経の理解を一変させました。
観経疏の言葉
その『観経疏』の「玄義分」に次のような一節があります。
経といふは経(たて)なり。
経(たて)能(よ)く緯(ぬき)を持(たも)ちて疋丈(ひつじょう)を成(じょう)ずることを得て、その丈用(じょうゆう)あり。
つまり、お経とは、たて糸であるというのです。そのたて糸が、緯(ぬき)、横糸を受け止めて、疋丈(ひつじょう)、つまり布を織り上げることができる。そしてその布は、織物としてのはたらきをなすことができるという意味です。
たて糸と横糸
良い布を織るためには、まずたて糸をしっかりと張る必要があるそうです。たて糸がグニャグニャしていたら、どれだけ横糸を渡しても、しっかりとしたいい布にはならないのです。
私たちの人生で譬えたならば、たて糸は人生を貫く根本線というか柱のようなものだと思います。それがお経だと善導大師はおっしゃるのです。では、横糸は何かといったら、それは人生における様々な経験です。
私たちは毎日の生活の中で、いろいろな経験をしています。それが横糸なのです。私たちは楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、毎日いろいろな経験をしているのですが、その経験もお経というたて糸がしっかりと張ってないと、人生という布はしっかりと織り上がらない。結局、こんな事があったな、あんな事もあったなで終わってしまい、その経験を握りしめて絶対化してしまいます。
経験が意味を持つ
しかし、その人生にたて糸がしっかりと張ってあれば、その経験がたて糸に照らされて意味を持ってくる。例えば、あのことは辛い経験だったけれど、そのお陰で自分の傲慢さに気づけたというように、人生という布が織り上がった時に、自分がその人生を生きてきた意味が、そこに開かれてくるのです。しかし、たて糸がしっかりと張ってなければ、ただ思い出だけを握りしめて、人生に意味を見い出すことなく終わってしまうのではないでしょうか。
お経という言葉に、善導大師はたて糸を張ることの大事さを私たちに教えてくれているのです。私たちも仏法を聴聞して、日々の生活に人生のたて糸をしっかりと張りたいものです。